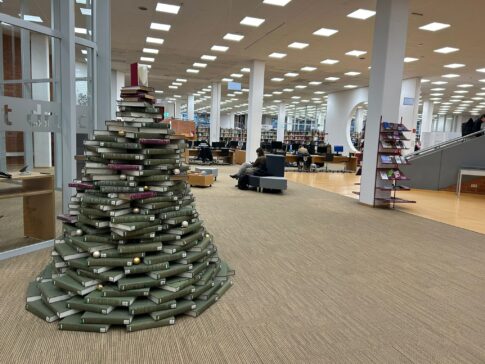2024年9月から2025年1月までイギリスのセントラル・ランカシャー大学に交換留学をしていた、法文学部人文学科多元地域文化コース2年の豊川利彩子です。今回は、私が留学生活を通して気づいたイギリスの食文化の多様性についてお伝えしたいと思います。
みなさんは、「ベジタリアン対応食品」や「ハラールフード」について耳にしたことがありますか。近年では、日本でも食事に気を使う人が増え、ムスリム圏からの観光客も増えている影響で、様々な場面でこれらの言葉を耳にする機会が増えたような気がします。私は、留学前にインドネシアからの留学生と関わる機会があり、その時に食べられない食べ物があるということで少し「ハラールフード」について学んだことがありましたが、あまり日常生活の中でこれらの観点に注目したことはなく、知識も十分ではありませんでした。
しかし、イギリスに留学してからこれらのことについて興味をもつようになりました。そのきっかけの1つは、イスラム教である友達との出会いでした。彼女は、イスラム教であるため豚肉やアルコール類など宗教上の理由で食べられない食べ物がありました。イギリスは多文化社会であるため、イスラム教の人は多く、私の留学先の大学にもイスラム教の学生が多くいました。イギリスでは、ムスリム圏からの外国人訪問者が増えていることにより、どんどんハラールに対応する社会が発達してきています。私の友達にハラールフードについて話した時に、イギリスはハラールフードが非常に充実しているため、これまでこのことに関して困ったことはないと言っていました。彼女は宗教上の理由で食べることが禁止されている食べ物がいくつかあり、困惑することもありますが、イギリスで作られた多くのハラール対応の食品にはマークがついているため、買い物の際に非常に役に立つと言っていました。特に私が驚いたのは、ゼラチンでした。お菓子やスイーツの材料として使われることが多いため判別が非常に難しいです。その時にこのマークは役に立つと言っていました。
また、私はハラールについてもっと知りたいと思い、友達に紹介してもらい、大学近くのアラビア料理のレストランに行き、食事をしてインタビューを行いました。そのレストランは、全てハラール・ヴィーガン対応のメニューでした。お客さんは、アラビア圏の人はもちろん、日本人を含むアジア人のお客さんも多いようです。そのため、中国語で書かれたメニューもあります。また、大学が提供している食事パーティでもハラール対応のメニューが必ず準備されています。


その後、私はハラール以外の食文化に関しても興味を持ち、ベジタリアンやヴィーガンに対応した食品についても調べました。これらは、環境保護や健康など様々な理由のために、動物性食品を避け、植物性食品を中心に生活する人のことです。イギリスはヴィーガン発祥の地で、1940年代にイギリスでヴィーガンというライフスタイルが誕生し、「Veganuary」という非営利団体が主催している、毎月1月をヴィーガン月間にしようという取り組みもあります。具体的な取り組みとしては、1月はイギリスの多くの地域でヴィーガンの知識を広めるためのイベントが行われたり、多くのレストランやパブで1月限定のヴィーガンメニューが提供されたりします。これらの食品に関しても、やはりハラールと同様にスーパーマーケットの食品には分かりやすいようにマークが付けられていて、留学期間中イギリス国内様々なレストランに行きましたがほとんどのお店で、これらの文化に対応したメニューが用意されていました。



ウェブサイトの情報によると、2024年の時点で世界でヴィーガンであると推定されている人の割合は、14%に上ります。日本には毎年様々な国から外国人が訪れているにも関わらず、このような多様な食文化に対応したレストランが少ないように感じます。グローバル化が進んでいく中でこのような様々な食文化のニーズに対応した社会を作り上げていくことは非常に重要なことではないかと考えます。スーパーマーケットやレストランなど人々の日常生活の中にこの食文化の多様性を取り入れることで、日本でもこれらの文化に興味を持つ人が増えていけばいいなと思います。